~目次~
1. 非認知能力ってなに?
🔍 認知能力との違いは?
2. 非認知能力の土台とは
🔍 幼稚園と家庭、両方で育てるバランスも大切
3. 非認知能力を伸ばす5つの関わり方
①自由に遊ぶ時間を大切にする
②小さな選択を任せてみる
③最後まで見守る
④感情に名前をつけて伝える
⑤「ありがとう」「がんばったね」と共感する
4. 「がんばれ」より「大丈夫」
✅ ママの声かけひとつで、子どもの心は変わる
✅ ママ自身も「がんばりすぎない」こと
「非認知能力って、最近よく聞くけど…」
「結局、家では何をしてあげればいいんだろう…?」

うちの子、まだひらがなも書けないんです。
何か勉強させたほうがいいですか?



文字よりもまず、“できた”をたくさん経験させてあげてくださいね。
今は“自信”の土台を育てる時期ですから
子どもの“生きる力”を支える「非認知能力」。
目には見えにくいけれど、将来にわたってとても大切な力です。
✅ 自己肯定感
✅ やり抜く力
✅ 思いやり
✅ 感情のコントロール
こうした力は、テストでは測れません。
でも、日々の関わりの中で、少しずつ、確実に育っていきます。
この記事では、
新米ママでも無理なくできる、家庭での“非認知能力の育て方”を、
焼津中央幼稚園の視点を交えてお伝えします。


1. 非認知能力ってなに?なぜ今注目されているの?
「非認知能力って、難しそう…」
そんなふうに感じる方もいるかもしれません。
でも実は、毎日の子育ての中で自然と育っていく力なんです。



非認知能力とは、“数値では測れない力”のことなんですよ
たとえば――
✅ 最後までやりとげる「粘り強さ」
✅ 自分の気持ちを切り替える「感情コントロール」
✅ 人の気持ちを思いやる「共感力」
✅ 失敗してもまた挑戦する「チャレンジ精神」
✅ 自分で考え判断する「主体性」
こういった力は、テストの点数や知識とは違い、
「人として生きていく土台」になるものです。
🔍 認知能力との違いは?
- 認知能力:IQ、語彙力、計算力など「目に見える学力」
- 非認知能力:感情・態度・意欲・対人関係など「目に見えにくい力」
近年では「学力」だけではなく、
非認知能力こそが将来の社会的成功や幸福感につながるという研究結果も増えており、
文部科学省でも幼児教育での育成が推進されています。
だからこそ、「今のうちからどう関わるか」がとても大切なんです。
次は、幼児期が非認知能力の“伸びどき”である理由をお伝えします。


2. 幼児期こそ伸ばしたい!非認知能力の土台とは
「非認知能力って、小学校に入ってからでいいんじゃないの?」
そう思われる方もいるかもしれません。
でも、実は3〜6歳の幼児期こそ“心の土台”が育つ大事な時期なんです。



“どうせ無理”じゃなくて、“やってみよう”と思える子に育てたいですよね
この時期の子どもは、
周りの大人との関わりや、日常の出来事を通して
「自分ってこういう人間なんだ」という感覚を少しずつ育んでいきます。
たとえば――
✅ 失敗しても見守ってくれる
✅ できたことを一緒に喜んでくれる
✅ 気持ちをわかろうとしてくれる
そんな日常の中で、
子どもは「やっていいんだ」「話していいんだ」「大丈夫なんだ」と感じていきます。
🔍 幼稚園と家庭、両方で育てるバランスも大切
園では先生やお友達との関わりの中で、
「順番を待つ」「気持ちを言葉にする」などの経験が増えていきます。
一方で、家庭では子どもが“素の自分”でいられる安心感があります。
その中で「甘え」と「挑戦」をバランスよく繰り返すことで、
非認知能力は自然と育っていくのです。



おうちでは“できなくてもいいよ”って言ってあげてください。
それが“やってみよう”につながるんです
次は、そんな非認知能力を家庭で楽しく育てる方法をご紹介します。


3. 家庭でできる!非認知能力を伸ばす5つの関わり方
非認知能力は、特別な教材やトレーニングがなくても、家庭の中で十分に育てることができます。
大切なのは、ママやパパが“どう関わるか”。
ここでは、すぐに実践できる5つの関わり方をご紹介します。
① 自由に遊ぶ時間を大切にする



“ただ遊んでるだけ”の中に、たくさんの学びがあるんですよ
自由遊びは、子どもの主体性や創造力、集中力を育てます。
ブロック、おままごと、積み木…どんな遊びでもOK!
「こうやってみようかな?」という思考の芽が、非認知能力につながっています。
② 小さな選択を任せてみる
「今日は赤い靴にする?青い靴にする?」
そんな簡単な選択肢でも、子どもは「自分で決められた!」という達成感を味わいます。
選ぶ経験は、自立心や自己肯定感の育成に直結します。
③ 最後まで見守る
子どもが時間をかけて靴を履こうとしているとき。
つい手を出したくなってしまうこと、ありますよね。
でも、そこをグッとこらえて見守ることも、
「できた!」という自信を育てる大切な関わりです。
④ 感情に名前をつけて伝える
「悔しかったんだね」
「嬉しかったね」
「ちょっとびっくりしちゃったかな?」
子どもの感情に言葉を添えてあげることで、
感情のコントロール力や共感力が育っていきます。
⑤ 「ありがとう」「がんばったね」と共感する
できたことを褒めるだけでなく、
努力や過程を一緒に認めることで、やる気や忍耐力が育ちます。



“できたからえらい”じゃなくて、“がんばったからえらい”って伝えてあげてくださいね
子どもの心が動く瞬間を、そっと支える。
それだけで、非認知能力はしっかり育っていきます。
次はラスト、そんな関わりの中でママが忘れてはいけない“心の余裕”についてお伝えします。


4. 「がんばれ」より「大丈夫」|ママの関わりが未来を変える
子どもには、強くたくましく育ってほしい――。
そう願うママほど、つい「がんばって!」「泣かないで!」と声をかけたくなることもありますよね。
でも、非認知能力を育てるうえで、本当に大切なのは、
がんばらせることではなく、“安心できる土台”をつくることです。



“がんばれ”の代わりに、“大丈夫だよ”と言ってあげてくださいね。
ママの安心感が、子どもにとってのエネルギーになりますよ
✅ ママの声かけひとつで、子どもの心は変わる
たとえば――
・「失敗してもいいよ」
・「最後までよくがんばったね」
・「やってみようと思ったことが、えらいね」
こうした声かけは、子どもの心に「やってみよう」の種をまきます。
その積み重ねが、折れにくい心・自分を信じる力を育てていくのです。
✅ ママ自身も「がんばりすぎない」こと
子どもに余裕を与えたいなら、まずはママ自身が“安心できる場所”にいることが大切です。
できない日があってもいい。
イライラしてしまう日もあって当たり前。



ママが笑っていると、子どもは“自分も大丈夫”って思えるんですよ
非認知能力は、特別なことをしなくても、
ママとの日々のやりとりの中で、自然と育っていく力です。
焼津中央幼稚園でも、子どもたちの“心の育ち”を丁寧に見守りながら、
ご家庭と連携して、一人ひとりの力を引き出す保育を大切にしています。
焦らず、比べず、寄り添って。
子どもの“今”を大切にすることが、未来の土台になります。
🍀見学やご質問はいつでも歓迎しています。
ぜひこちらからお問い合わせくださいね。
👉お問い合わせフォーム
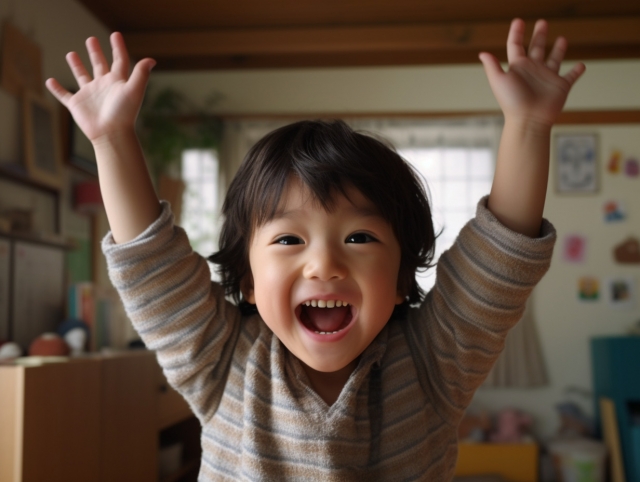
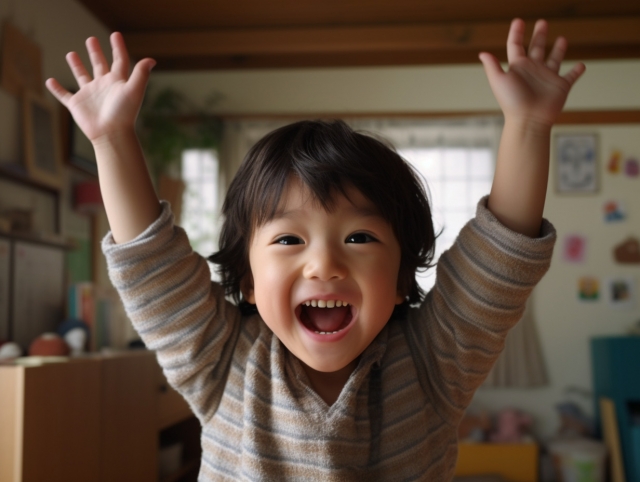
#非認知能力 #非認知能力育て方 #幼児期非認知能力 #家庭教育 #子ども自己肯定感 #感情コントロール #親子コミュニケーション #新米ママ子育て #幼児教育 #焼津中央幼稚園





